感染症流行期にみる「音」・「音楽」を介在したコミュニケーションの今昔
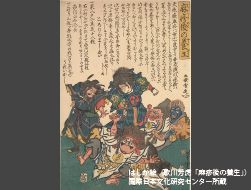
Vol.003
2022.07.17
光平 有希
国際日本文化研究センター
過去の音楽と感染症との歴史を振り返ってみると、様々な病との遭遇によって生み出された音楽作品があることに気づきます。それらの音楽は回復を祈る治療儀礼の一環として作られたものであったり、あるいは八方ふさがりの現状を嘆き、感情を吐露するツールとして用いられたり…といった具合に種々の性格を孕はらんでもいます。さらに、感染症を契機に音楽自体の様式や形式、音楽を伝える手段時自体、変化を強いられる場面もありました。
いま、コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、これまで当たり前のように行われてきたライブ会場やホールでの音楽鑑賞ができなくなり、それを打破するかのようにオンラインでの音楽配信が急加速度的に拡がりをみせています。また、配信するだけでなく、聞き手からの意見をも踏まえて次回のプログラムや演奏形態を検討する、そういった双方向コミュニケーションによる音楽活動も広まっています。
そうした、リアルタイムでの音楽変容まっただなかで、これから演奏家や作曲家を目指す、あるいは音楽教育に携わろうと考えている音大生は現状をどのように捉えているのでしょうか。音楽療法史、医療文化史を研究する筆者が、とりわけ過去の感染症史やクラシック音楽界と絡めながら、東京・大阪・京都の音大に通う現役大学院生4名(修士・博士課程在籍者)とZoomをつなぎ、オンライン上で話をしてみました。
記事一覧




