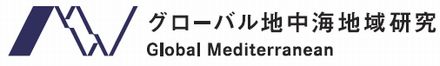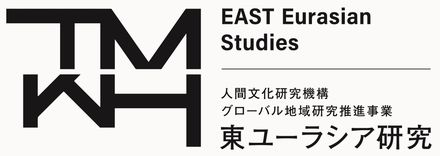ネットワーク型基幹研究プロジェクト
他の大学や研究機関と連携して実施するプロジェクト
機構内の機関が中核となって国内外の大学等研究機関とネットワークを形成し、我が国及び世界にとって重要な課題を掲げて実施するプロジェクトです。2つの課題を設定し、研究フィールドから課題解決を実現する研究に取り組みます。
 グローバル地域研究推進事業
グローバル地域研究推進事業
(総括班:国立民族学博物館)
これまで主にポストコロニアルな世界認識の下で想像(創造)された地域それぞれの固有性を内在的・本質的に明らかにすることに注力していた地域研究を刷新し、グローバル秩序の構築(とその失敗)と変容のメカニズムを、諸地域の比較と関連性という視点から明らかにすること、さらには従来の固定的な地域像を越える地域研究を模索することを目的とし、次の4つのプロジェクトを設置して、ネットワーク型の地域研究を推進します。
近現代の地中海を介した人・モノ・知識の往来を超地域的/学際的に考察し、地域研究の枠組みを探求します。
- 中心拠点 国立民族学博物館
- 移動の近代と地域概念の再構築
- 東洋大学
- 「イメージ/表象」の歴史的変遷
- 東京外国語大学
- 文学・芸能の文明圏間環流
- 同志社大学
- 「多文化主義」と現代の共生
インド洋をとりまく世界に焦点を合わせ、ヒト、モノ、情報、価値等の流動がこの世界内外での様々な関係性の生成・発展・蓄積あるいは消滅に関わってきた動態を解明します。
- 中心拠点 国立民族学博物館
- 移動の連関性と連続性
- 東京大学
- 開発と環境、医療の持続性
- 大阪大学
- 文学・思想の混交性と創造性
- 京都大学
- 平和的共生の可能性
「オーストロネシア」語族圏としての基層文化的な共通性を軸に、海域アジアからオセアニアにおけるヒトやモノ、情報をめぐる越境的な動きに関わる総合的な把握を目指します。
- 中心拠点 国立民族学博物館
- 資源・インフラ開発、生業、 文化遺産、文化復興
- 京都大学
- 食と健康、身体的・生理的・文化的適応、気候と社会の変動
- 東洋大学
- 海辺居住の論理、自然災害、レジリエンス、共通性と地域性
- 東京都立大学
- 人とモノの流動性、経済資本と移動、マテリアリティと景観の変遷
巨大国家である中国とロシアを抱える東ユーラシアの存在がグローバル世界に及ぼす影響力を、文化の衝突とウェルビーイング(幸福感)という視点で解明することを目指します。
- 中心拠点 東北大学
- マイノリティの権利とメディア
- 国立民族学博物館
- 宗教とサブカルチャー
- 神戸大学
- 少子高齢化と葛藤
- 北海道大学
- 越境とジェンダー
機構(主導機関:歴博)、東北大学、神戸大学が中核となり、日本各地の大学や地域に設立されている「資料ネット」と連携して、歴史文化資料の調査および保存研究活動を軸とした全国ネットワークを構築します。また、地域における歴史文化の基盤を研究者だけでなく地域全体で認識することで、地域歴史文化の構築研究に資するとともに、自治体や社会との協働・共創による資料保全のあり方や地域文化の基盤を研究者と地域が共有する事業へとつなげていくことを目指します。

市民・学生・研究者等の相互連携による
地域資料の調査・整理活動(山形大学)
・震災資料をふくむ現代資料の保存・活用研究