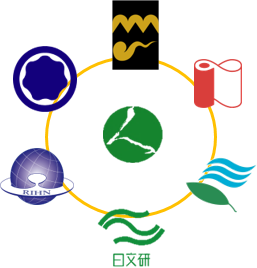〈危機〉の時代に ―人文知からのメッセージ―
〈危機〉に立ち向かう人文知
21世紀における人類にとってもっとも重要で緊急の課題は、人類の存続と共生です。環境問題・資源枯渇・感染症など多くの困難がある中で、人類は地球上でいかに存続し、戦争・テロリズム・暴力・差別・貧困などに抗して、いかに共生していくのか。
それらの問題を根源的に解決する鍵は、人間文化にあります。人間文化に関する学問は、人間・文化・社会・自然を対象とします。人文学とは「人間とその文化を総合的に探究する学問」であり、総合性が本来の人文学のあり方です。今、人文学の細分化が著しい中、「人間とその文化」を俯瞰することのできる大きな研究の総合化に基づく〝分厚いヒューマニティーズ″が強く求められています。それが文と理を超越した知の総体としての「人文知」です。
2019年10月には、当機構の経営協議会における外部委員の発言を契機として、経済・文学・美術・自然科学・マスコミなど、各界の著名人、計10名が結集し、「人文知応援フォーラム」が設立されました。そこでは、「人文知」が日本社会の中で広く生かされるよう、多くの人たちと連携しながら応援活動をすると宣言されています。
現在、世界中を恐怖に陥れている新型コロナウイルスに、われわれはどのように立ち向かえばよいのでしょうか。『感染症と文明』の著書で知られる山本太郎氏(長崎大学熱帯医学研究所教授)は「感染症が人間の社会で定着するには、農耕が本格的に始まって人口が増え、数十万人規模の都市が成立することが必要であった。」「文明は感染症のゆりかご」だと指摘されました。
そうだとすれば、われわれはこのウイルスと共生していかなければなりません。その恐怖が引き起こす人類社会の分断と偏見・差別に打ち勝って、この危機の本質とは何かを広い空間軸と長い時間軸の中で問い直し、文明を再構築していく視点をもつことが欠かせません。このコーナーには、この〈危機〉の時代にあって、当機構を構成する6つの人文系研究機関の研究者が、それぞれの専門分野の立場から、人文知を見すえて発信したメッセージを集めています。
2020年4月
人間文化研究機構 機構長
平川 南
記事公開日:2021年1月6日
豪感染拡大がやまないコロナ禍の中、それでも科学的根拠のある対策が講じられて効果が期待され、一方で気候変動の予測の精度もあがっています。しかしはかり知れない未来への私たちの不安は払しょくされることがありません。人類が「未来を考える」ということは、地球の、そして宇宙の「はかりしれなさ」に対する畏敬の感情をもちつつ、「はかる」行為を続け、あらたな可能性を考えていくことではないでしょうか。
記事公開日:2020年9月1日
豪雨災害をもたらした長い梅雨に続く酷暑の夏、そしてゲリラ豪雨。世界各地からは異常高温による森林火災も多数報告されています。日本に豪雨災害をもたらした要因は、非常に強い高気圧に加え、海水温の上昇による水蒸気の増加があります。日本付近も含めた全球的な海面水温の上昇は、CO2などの温室効果ガス増加による「地球温暖化」の海洋に現れた結果とされています。COVID-19のパンデミックからの社会・経済の回復は、より持続可能な新しい社会への転換の可能性を求めていく「緑の回復(Green Recovery*)」をめざすべきです。
記事公開日:2020年7月28日
新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)によって引き起こされた「危機」に際して、人文学の研究者は何をすべきか。また、研究と社会をつなぐ人文知コミュニケーターに今できることは何か。そういう問いから、人文知コミュニケーター初の共同企画「くらしに人文知~コロナ時代を生き抜く」の連載を始める運びとなりました。人文知コミュニケーター独自の眼差しで、人間文化研究機構内外の研究者との対談や、関係者のインタビューなどを掲載していく予定です。第1回目の記事として、連載のコンセプトやテーマについて、自らの経験を交えながら率直に語り合った内容をお届けします。この議論自体が人文学の役割を考える小さな糸口になれば幸いです。
記事公開日:2020年5月28日
日本が少なくとも現時点で感染拡大をかなり抑制できているのは、そのような法律の制定よりもまず、地域レベルでの民主主義的施策と行動こそが重要であることを強く示唆しています。
記事公開日:2020年5月8日
新型コロナウィルス(covid-19)の感染拡大は私たちの生活を一変させ個人と社会、国家と国際秩序の間の関係をも大きく変えないではおかない状勢にある。ポストcovid-19の世界に対して人文知は何ができるのかを考える。
記事公開日:2020年5月6日
私たちは、今、人類がこれまで経験したことのない局面にいやおうなく立ち会うことになりました。
その局面下に私たちに求められていることとは。
国立民族学博物館長吉田憲司が「過去の感染症の例をひもときながら、その共通性を考察し、さらに新型コロナウイルスに対してどのような意識を求められるか」を館長だよりにて発信しておりますので、ご覧ください。
記事公開日:2020年4月24日
江戸時代、日本列島の人々が疫病をはじめ様々な災いと闘い、乗り越えてきました。同じように、私たちも今の状況を乗り越える時が必ず来ます。古典文学には、今に役立つ有益な情報が美しく豊かな絵と共に記されています。その一端を国文学研究資料館のキャンベル館長が動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。
記事公開日:2020年4月6日
新型コロナウイルス(COVID-19)感染症によるパンデミックに陥った世界。この危機を乗り越えることが喫緊の課題ですが、今回の危機を未来可能な都市や社会への転換にどう生かせるか、私たち人類の叡智と想像力が試されています。
記事公開日:2020年3月11日
新型コロナウイルス感染症の影響が日本国内でも多方面に出ている昨今、日本に生きる現代の私たちへ歴史資料だからこそ語ってくれるメッセージがあるのではないか――。