調査研究の現場から@ワシントンD.C. 総合地球環境学研究所 澤崎 賢一さん

人間文化研究機構では、機構のプロジェクトの推進及び若手研究者の海外における研究の機会(調査研究、国際研究集会等での発表等)を支援することを目的として、基幹研究プロジェクト・共創先導プロジェクトに参画する若手研究者を海外の大学等研究機関及び国際研究集会等に派遣しています。
今回は、米国に派遣された総合地球環境学研究所の澤崎 賢一(さわざき けんいち)さんからの報告です。
NIHU若手研究者海外派遣プログラムのサポートを受けて、アメリカのワシントンD.C.に2024年8月6日から9月10日までの約1ヶ月間、個人/共同研究を発展させるために滞在しました。渡航前に設定した研究テーマは「科学知/在来知の分断を越えた協創知の創出:人新世に必要なコモンズ型映像対話(Co-creation of Collaborative Knowledge Beyond the Divide of Scientific and Indigenous Knowledge: Commons-based Visual Dialogue for the Anthropocene)」です。今回の派遣を経て、この個人研究のテーマは共同研究「持続可能な未来を実現するためのナラティブ表現を用いた意思決定に関する実践的研究」へと発展的に変更になりました。
僕はこれまでアーティスト/映像作家として活動してきました。同時に近年、研究者として、知の生成プロセスにおいて様々な観点からコミュニケーションを交差・発展させるためのナラティブな方法論(特に映像を活用)をプロジェクト・ベースドで学際的に研究しています。
最初に、今回のワシントンでの意見交換の際の重要なキーワードである〈メタ映画(Meta-Film)〉と〈コモンズ映画(Commons-Film)〉という映像制作の手法についてお話しておきます。
〈メタ映画〉とは、映像を鑑賞したフィードバックをナレーションによって映像内にメタ的に入れ込んだ映像制作のことです。メタ的な視点からプロジェクトの参加者が映像制作工程を共に振り返りながら、調査研究プロセスにおける体験がもつ価値に新しい視座を与えます。この手法を用いた作品に、多重層的ドキュメンタリー映画『#まなざしのかたち(#manazashi)』(監督:澤崎賢一, 124分, 2021年, 国内外受賞多数)があります。本作では、フィールド研究者のアフリカ・東南アジアなどの調査現場における感性的な側面に着目し、映像芸術を活かしてそれらを可視化・顕在化させるための表現手法として、「映像を見ることで感じたこと」を映画内にヴォイスオーバーとして挿入しています。ここで明らかになったのは、学術研究の感性的な部分とイメージに関わる芸術表現がメタ的な視点において重なり合い、分野を横断した共創によって、双方にとっての気付きや学びの場が創出されたことです。

〈コモンズ映画〉とは、調査対象者を含め、プロジェクトの参加者全員がカメラで互いを撮影し合い、クラウド上にアップロードされた映像素材を共有資源として、各自の価値観や想いに基づき映像制作に取り組むことです。この手法を用いた先行事例として、プロジェクト「ヤングムスリムの窓:芸術と学問のクロスワーク(Young Muslim’s Eyes: Crosswork between Arts and Studies)」(共同代表:澤崎賢一, 野中葉・慶應義塾大学, 阿毛香絵・京都大学)があります。このプロジェクトにおいて特徴的なのは、映像メディアを表現手段としてのみならず、一種のハブとして活用し、立場や専門、世代や文化的背景の異なるアクターが相互に関わり合う研究/共創の場が生み出されたことです。

今回のワシントンD.C.での意見交換の背景には、〈メタ/コモンズ映画(Meta/Commons-Film)〉という手法を、それらが生まれたコンテクストとは全く異なるコンテクストにおいて、どのように機能しうるのか、という問いがありました。結論からお話しておきますと、この〈メタ/コモンズ映画〉の異なるコンテクスト上での可能性を拓く特徴は、大きく2つあります。
ワシントンD.C.での僕のホストは、KLASICA(Knowledge, Learning and Societal Change Alliance)の議長でアリゾナ州立大学の特任教授でもあるイラン・チャバイ(Ilan Chabay)さん、それからKLASICAの共同ディレクターであり アメリカ国立標準技術研究所(NIST)のリサーチ・エコノミストであるジェニファー・ヘルゲソン(Jennifer Helgeson)さんでした。
今回の滞在では、KLASICA のイランさんとジェニファーさんにアレンジをしていただき、1.アメリカ国立標準技術研究所(NIST)、2.ハーシュホーン・ミュージアム(Hirshhorn Museum)の方々と意見交換をさせていただきました。また、3.アリゾナ州立大学ディシジョン・シアター(Decision Theater at Arizona State University)での視察も行いました。それらのディスカッションや視察を踏まえて、4.KLASICAのイランさんやジェニファーさん、同じくKLASICAの共同ティレクターであるデビッド・マッグス(David Maggs)さんらと今後の可能性について議論を重ね、共著での論考「Combining Art, Sciences, and Technology in Inclusive Decision Making for Community Resilience and Sustainable Futures(アート、サイエンス、テクノロジーを組み合わせた包括的な意思決定が、コミュニティのレジリエンスと持続可能な未来を実現する)」(著者:イラン・チャバイ, ジェニファー・ヘルゲソン, デビッド・マッグス, 澤崎賢一)にまとめました。この論考は今後、国際ジャーナルへの投稿を目指して帰国後の現在(2024年12月)も執筆を進めています。また、2025年2月11日には、RIHN-KLASICAワークショップが総合地球環境学研究所で開催される予定で、地球環境問題の解決に向けて科学とアートの協働はいかにあるのが望ましいかを議論する予定です。



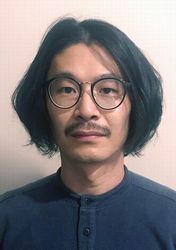
澤崎 賢一(さわざき けんいち)
総合地球環境学研究所 特任助教
アーティスト/映像作家/キュレーター。博士(美術)。
プロジェクト「ヤングムスリムの窓:芸術と学問のクロスワーク」を共同主宰。主な作品に、多重層的ドキュメンタリー映画『#まなざしのかたち』(監督:澤崎賢一, 124分, 2021年, 国内外受賞多数)。劇場公開映画『動いている庭』(監督:澤崎賢一, 85分, 2016年, 第8回恵比寿映像祭プレミア上映)など。
個人ウェブサイト:https://texsite.net




