人文知コミュニケーター企画 異分野連携に向けた対話
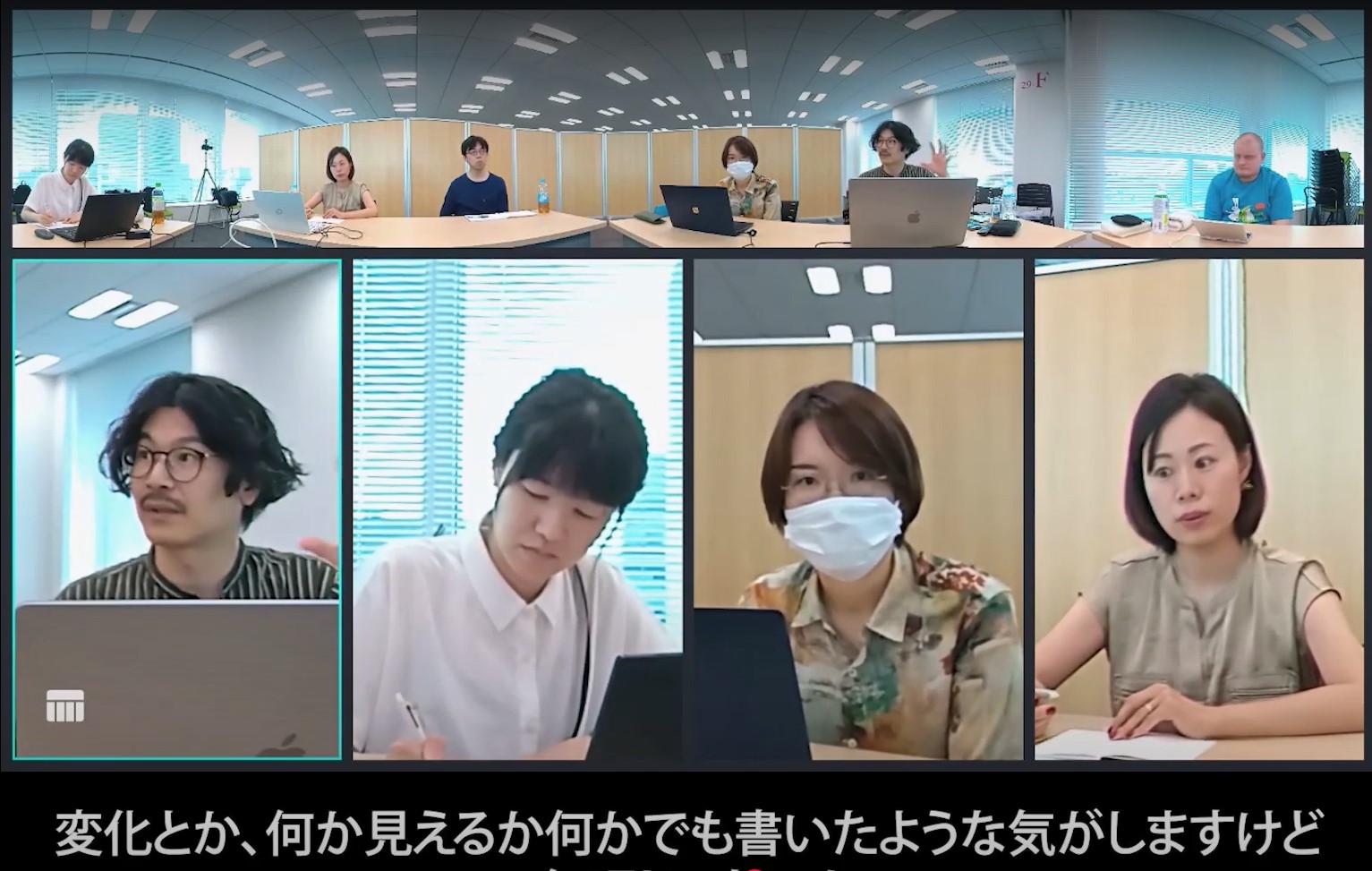
人間文化研究機構では、2017年度から博士号を取得した若手研究者を「人文知コミュニケーター 」として雇用・養成しています。各コミュニケーターの活動について、これまでNIHU MAGAZINEにて紹介してきました。今回は個人ではなく、集団としてのコミュニケーターの活動を取り上げます。
人文知コミュニケーターの活動は多岐に渡ります。その一例が月に一度の研究会です。オンラインや対面にて人文知コミュニケーターが集まり、各自の研究や今後の企画について話し合います。昨年度の企画の1つが異分野連携に向けた対話でした。
一緒にどんな研究ができるのか。そのための対話の場を設け、6名のうち5名の人文知コミュニケーターと拙著(専門 西洋建築史)が参加しました。3時間を超える対話の様子をビデオ録画し、次回の対話用のデータとしました。他にも動画を短く編集し、筑波大学大学院での集中講義(人文知コミュニケーション:人文社会科学と自然科学の壁を超える)用の教材として活用しました。
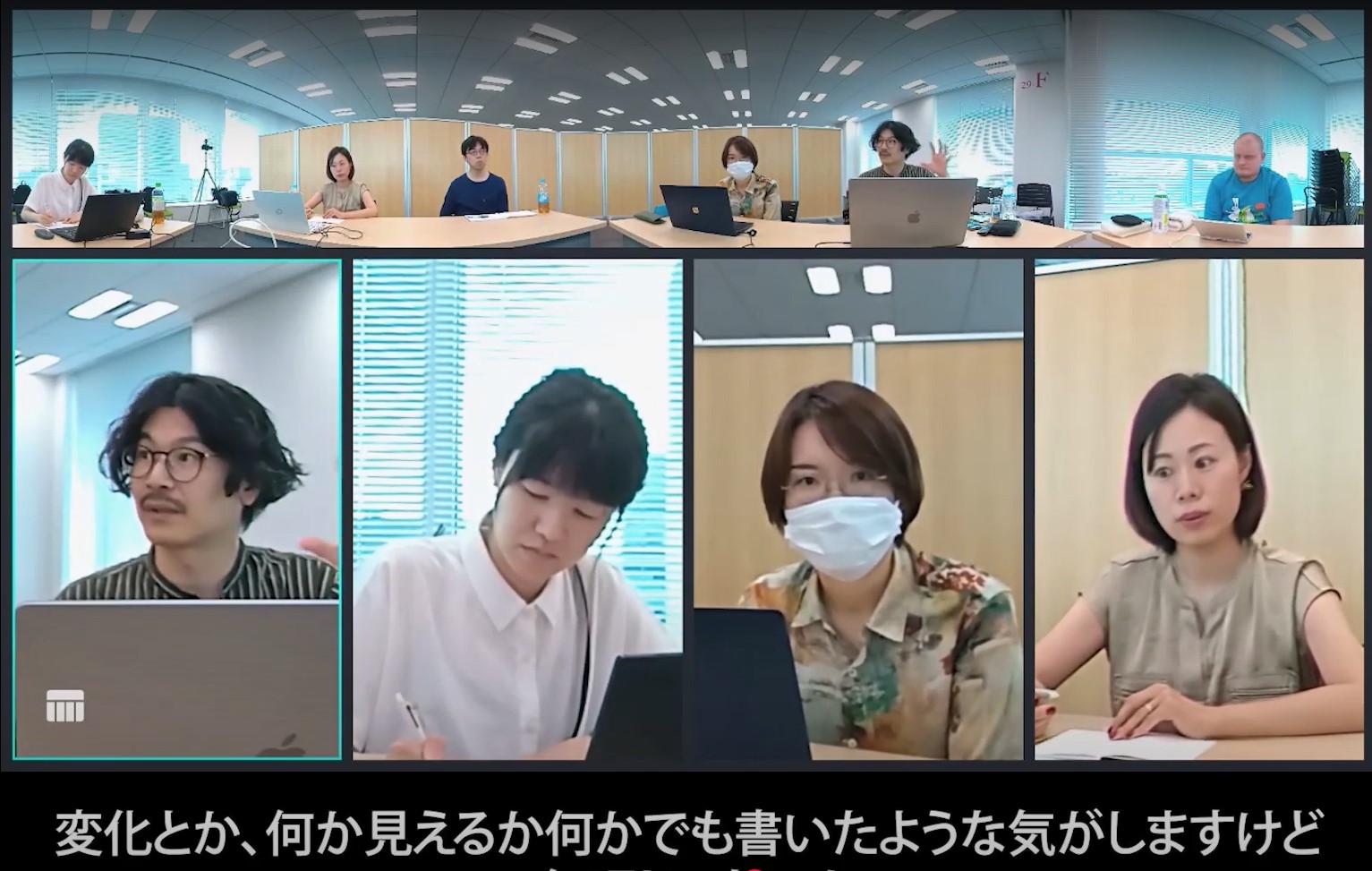
今回の対話ではいくつもの発見、もしくは連携のために踏まえるべき点がありました。たとえば研究対象が文書か、あるいはフィールド調査かによって研究データの収集方法が変わります。文学研究を含む前者の場合、まず研究者が図書館や古文書といった文書の収蔵先、もしくはデータベースにアクセスします。続いて書物に描かれている文字・絵・地図(データ)を元に、それらの意味や描写の経緯、解釈等を考えます。対するフィールド研究は研究者が現地へ赴き、現地の言語や方言を使った現地の方々との交流を研究データとして扱います。
こうした研究アプローチの違いをお互いに知ることが、異分野連携に向けた一歩になります。しかしそれだけでは対話が続きません。実は対話の前に以下の2点を実施しました。
テーマ: 戦争アニメの表象、中近世の和歌の注釈書、沖永良部島の方言の保存と継承、桐雄夏生の小説に見る女性や犯罪の表象、映像芸術、ネパール・カトマンズの初潮儀礼
| No. | 参加 候補者 |
テーマ | 内容 |
| 1 | 河田 横山 |
(イベント)対面で行う翻刻 | 中世や近世、現代の日本語(方言を含む)が対象 |
| 2 | 古典籍からみた沖永良部島の歴史や伝承 | 沖永良部島にある古典籍を通して、島の歴史(例 薩摩藩との対外関係)や伝承を紐解く | |
| 3 | 横山 駒居 澤崎 |
島の女性と労働 | 沖永良部島を舞台に、島の女性の労働状況を調査する研究者の映像ドキュメンタリー |
| 4 | アルト 澤崎 大場 |
戦争アニメにおける建築や都市の表象と変容 | 「はだしのゲン」等の戦争作品に登場する原爆ドームといった建築、広島や東京といった都市を対象に、アニメの描写と現在の姿を比較する映像ドキュメンタリー |
| 5 | アルト 河田 駒居 |
弁当の今昔物語 (文学とアニメを対象に) |
中世や近世の古典作品にみる弁当、戦争アニメに登場する近現代の弁当、桐野夏生の小説に登場する現代の弁当を通して日本の弁当史を探る |
このように各コミュニケーターの研究発表を聞いて、共通するキーワード探しや各自の興味や関心事項を元に連携シートを記入し対話に臨みました。対話中にはシートの内容を深堀することで、発展可能な連携案を模索しました。
最後に、今回の対話は異分野連携の終着点ではなく出発点です。2025年度以降も話し合いの場を設け、本格的な異分野連携に向けて検討または事前調査をする予定です。
(文責:大場 豪 人間文化研究機構 人間文化研究創発センター 研究員)




