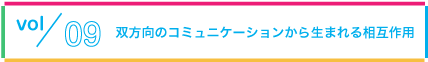

新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、私たち人文知コミュニケーターは研究者でありながら、生活者でもあるという立場から何ができるかを模索してきました。このウェブサイトは、そうした思いから生まれました。これからも身近な話題からちょっと難しい話まで、人文知コミュニケーターならではの視点で記事を発信していきます。
双方向のコミュニケーションから生まれる相互作用
工藤さくら 人文知コミュニケーター(人間文化研究機構 国立民族学博物館)


2023年12月5日に人文知コミュニケーション研究会(オンライン)が実施されました。
今回は、国立国語研究所の人文知コミュニケーターである横山晶子さんに「私の『人文知コミュニケーション』」と題して発表をしていただいています。ご本人曰く、人文知コミュニケーターの姿は、これまでご自身がやってきた活動にとても似ているとか。ちなみに人文知コミュニケーターという仕事は、研究と社会の双方向的なコミュニケーションを目的に設置された新しい制度です。所属する研究者は、それぞれの研究分野の経験を活かし、知の総体としての「人文知」の伝達・つながり・創造に励んでいます。ただしそれぞれが抱く「コミュニケーション」のあり方もまたさまざま。そのため、このような研究会をとおして他の研究者はどうそれを捉えて実現しているかを定期的に共有し合っています。この記事を書いている私自身、着任して1ヶ月の新人ですが、今回の横山さんのご発表から、どう社会に働きかけ関わっていくかについて多くの学びがありました。それでは横山さんのご発表内容に沿ってご紹介したいと思います。
横山晶子さんは、かれこれ13年以上、北琉球奄美群島の沖永良部島【おきのえらぶじま】のことばを言語学的に研究されています。
ご専門は、言語学、そして、社会学。
言語学を専門としつつも、社会学という研究環境に身を置いてきたということが、横山さんの研究活動において、従来の言語学研究のあり方とは異なる独自性を生んでいるようです。
キーワードは、「双方向のコミュニケーション」から生まれる「相互作用」です。
⑴ 研究活動
言語学の文法記述・記録と言語継承
ご研究は、沖永良部語の文法記述や記録が約8割、実は、残りの2割ほどが言語認識や言語継承・復興に関するものだそうです。継承・復興に関してはそこまで大きなウェートを占めていなかったと言います。ちなみに文法とは、母音や子音がいくつあるか(音韻)、動詞をどのように活用するか(形態)、あるいは語順がどうなっているか(統語)といったもので、専門家にとっては、特に危機言語と呼ばれる言語は、従来の学術的常識を覆す貴重なデータとして捉えられている一方で、一般の話者や専門外の人にとっては、「それに何の価値があるのか」と分かってもらいづらいこともしばしば……。しかし、こういった危機言語が継承という文脈と結びつくことによって、文法研究が社会的な意味を持ち始めてくるのだ、と横山さんは言います。
さて、言語の継承・復興ときくと、対外的にはイメージがいいですが、言語学・方言学の分野ではこういった主観的意思の介入はタブー視されています。私自身、正直なところ、この言葉に違和感を覚える一人でもあります。データ主義で客観性を重視する言語学のあり方は、一方的に言語を保存したり残そうと働きかけるといった主観的介入と相慣れないことが多いよう。横山さん自身もこういった継承・復興の活動に参加することについて躊躇があったそうです。しかし、社会学という研究環境で経験を積んだ横山さんは、文化人類学の動向や社会学のアクションリサーチ論を大学で学んだことで、ある意味吹っ切れたといいます。それは、自身がことばを通して他者と関わる際に、ただ観察し「何もしないこと」でも語外の意味が共有されていること、「研究者は透明人間になれない」ということ、そして何をしたって/しなくたってその社会に「影響」はあるということだったそうです。そして腹を決めた横山さん。次のようなスタンスで研究に向かうようになったといいます;
①言語は消えても良い、ただ、自分が関わった言語についてはできるだけ記録する
②人の意見は変えなくて良い、ただ、希望者には継承のお手伝いをする
これを聞いて、なんて冷たい人なんだ!と、もしかしたら思う人がいるかもしれませんが、言語学と社会学のどちらの学問も熟知してきた横山さんならではの誠実な向き合い方だと思います。この姿勢は、文化人類学的調査を行う私も強く共感するところで、いわゆる再帰人類学とよばれる過程において、研究者が民族誌を記述する中で、研究者自身が調査地の人びとと関わっている「自分」という主観性を無視してきた事実や、「書くこと」と書かれる対象の力関係など、調査のあり方や文化の記述の問題について猛省した時代の出来事とも通ずる部分があります。このように、研究者自身も“人として”関わり「自分が偏りを持ってることを意識した上でやる」ということは、単に研究は社会に貢献するものだというような一方方向の高慢さをなくすだけでなく、研究と社会との「双方向のコミュニケーション」を可能にするものだと思います。
学びポイント① 自分と調査地の人びと「双方向のコミュニケーション」
ことばを継承したい?理解したい?
驚くことに沖永良部語は方言とされながら日本語話者からの理解度は5%以下といわれ、ユネスコの「危機言語地図」にも掲載されています。そんな“希少”な方言(言語)を話す人たちはさぞ自分のことばに誇りをもち残していきたいと感じているだろうと思いきや、実際に言語認識や継承について現地で調査をしてみると、実は、「別に方言を残したいと思わない」と感じている人もいるといいます。そういった学術的な意味での「価値」は「継承すべき」のような押し付けにもなりかねず、現地の話者がどう感じているのかとは必ずしも一致しないということに気付かされます。横山さんは、社会学的な手法を使って、継承について島民がどう感じているのかアンケート調査を行い(横山晶子「沖永良部島民の言語意識資料––アンケート調査を元に––」[横山晶子Researchmap])、回答者の9割が継承を望んでいるということを明らかにしました。また、沖永良部語を話せないけれども"理解できる"、比較的継承が容易な「潜在話者」(パッシブスピーカー)に着目します。そして、30~60代という壮年期かつ子育て世代でもある彼らを後押しするようなマテリアルの制作を提案したそうです。絵本・教材の出版、解説動画の配信、語彙集データベース、ホームページの制作など子どもの教育に熱心な世代とつながったことで活動は広まっていったそうです。これは言い方を換えれば、どこにニーズがありどんなシーズ(自分の専門知識や技術)が活用できるかを体現したものといえるのではないでしょうか。一方的なソトからの押し付けにならないためにもニーズを理解するためのコミュニケーションが研究を進めていくうえで必要不可欠だということが分かります。
しかし研究者は常に調査地に居られるわけではありません。実際に横山さんも海外留学や妊娠・出産などのライフステージを経験され、またコロナ禍も現地にいくことができない時期が続いたそうです。「ソト」からの働きかけには限界があるし、それだけでは十分ではない、そして「研究者がいなくなった後も続くような構造づくり」に焦点をうつし、地域の中に、記録・継承をする人材を育成することに注力していくようになります。これまでのように研究者が現地に行くだけでなく、現地の人を東京に招いてワークショップを行ってもらったり、そういった行き来を繰り返す中で、経験を積んだ島民が他の島民に伝えていく、といったように、参加者に「役割」を渡していくようになりました。そうすることで、島民側からの自発的な動きにもつながっていったといいます。そして、2019年1月25日には、沖永良部島和泊町と国立国語研究所が方言継承のための連携協定を結ぶという形で、その後も、個人のレベルを越えた大きなつながりに結実していきます。
学びポイント② ニーズとシーズ、関わり合う中で生まれる自発的な意識を拾い上げる
言語(学)をとおして社会とつながる
言語学者として集落を一人で回っていた時に比べ、双方向的な関わりが増えていくにつれて、島の人たちが自発的に企画する語彙の収集や音声の記録などが増えたそうです。公民館講座などに集まった様々な集落の人たちが個人で数百枚にも及ぶ言語資料や、約2000語という膨大な語彙を収集してくる事もあったとか。また、協定を結んだことによって、全戸を対象とする言語意識調査がやりやすくなったり、国際連携による実証実験や、教育分野との枠組みづくりなどが進めやすくなったという効果もあったようです。様々なデータが島民側から集められ、今度は、研究者側が技術をもってそれを分析するという形で関わっていく、あるいは、10代を巻き込んだデータ蓄積、島で働く外国籍の人たちや医療・介護職にかかわる人たちに方言を使ってもらいコミュニケーションを生むサポートをしていく等、さまざまな「相互作用」が今でも起きているそうです。研究者ひとりができることには限界がある。そこで様々な双方向のコミュニケーションを生む構造を提供していくことで相乗効果が生まれていく。それによって「社会も科学も発展、前に進んでいくことができるのではないか」と横山さんは最後に話していました。
学びポイント③ さまざまな人が交わることで起こる「相互作用」
⑵ 横山さんの考える人文知コミュニケーションとは?
それは、「研究と社会を繋ぎ、双方向のコミュニケーションを促すこと」。理系のサイエンスコミュニケーターのように、まず専門的な知識をかみ砕いで解説するという以上に、人文知コミュニケーターの役割は、より実生活に近い部分にある疑問や諸問題に対して、直接的に科学にアプローチできるというところに強みがあると話します。こういったコミュニケーションはさまざまな分野ですでに実践されていて、人文学の場合はそれを言語化していくなかで理論化されていくものではないか、そのように科学と一般社会をつなぐことで、自然と社会と研究者の双方に貢献することが出来るのではないかと考えているそうです。
発表を受けて
横山さんのお話を受けてまず考えることは、研究という文脈では、コミュニケーションは、研究者と研究対象となる人や複数の集団間で双方向的に行われるべきだということです。双方向という関わり方が重要である理由は、対象のニーズや地域の課題を理解することにつながるだけでなく、当該調査地の人たちが自発的に物事を発信したり、企画していく潜在能力を拡大させていく可能性も秘めているからです。「研究は社会に役立つもの」という前提で研究活動を行う危険性について、研究者それぞれが社会への影響力や情報公開の責任が伴うものであることを十分に理解して関わっていくということがとても大事なことであると学びました。ただしこのコミュニケーションを可能にするためにはより長い歳月や関係性の構築が不可欠になります。もちろん人文知コミュニケーターという仕事は任期が決まっているものなので、新しくできることはかなり限られます。そういう点で、これまでの自分の研究活動なかで培ってきた人(人脈)・資源(情報、モノ、経験)をいかにコミュニケーションにつなげていくかが課題になってくるのではないかと思います。
