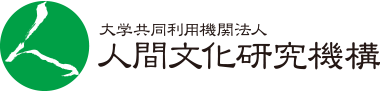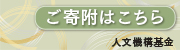イベント一覧
-
【民博】アイヌ工芸 in みんぱく
2017年11月30日カムイノミの開催にあわせて、「アイヌ工芸 in みんぱく」を開催します。公益社団法人北海道アイヌ協会主催の「北海道アイヌ伝統工芸展」において上位入賞を3回受けて認定された「優秀工芸師」の作品などを紹介します。期間中には、優秀工芸師による製作実演のほかに「もの作りワークショップ」も実施します。
アイヌ民族が培ってきたもの作りの技術や知恵、伝統から創造された数々の作品に、間近でふれてみませんか。観覧は無料です。多くのご来場をお待ちしています。
-
【民博】ミンパク オッタ カムイノミ(みんぱくでのカムイノミ)
2017年11月30日カムイノミとはアイヌ語でカムイ(神・霊的存在)に対して祈りを捧げる儀礼です。みんぱくでのカムイノミは、本館が所蔵するアイヌの標本資料の安全な保管と後世への確実な伝承を目的としています。以前は、本館展示のチセ(アイヌの伝統的な家屋)製作を監修した萱野(かやの)茂(しげる)氏(故人・萱野茂二風谷アイヌ資料館前館長)によって、非公開でおこなわれていました。萱野氏の没後、平成19(2007)年度からは、社団法人北海道ウタリ協会(現・公益社団法人北海道アイヌ協会)の会員がカムイノミと併せてアイヌ古式舞踊の演舞を実施し、公開しています。平成29年度は、八雲アイヌ協会・苫小牧アイヌ協会の方々にお越しいただき、開催いたします。
どなたでも見学できますので、ぜひお越しください。
-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「博物館の中の文化遺産、博物館の外の文化遺産」
2017年11月26日民族誌博物館は、くらしに息づく有形の文化遺産を保存し展示する役割を担っています。いっぽう、伝統的建造物群保存地区や文化的景観、無形文化遺産など、くらしの場で保存される遺産も少なくありません。両者をふまえて、くらしに関わる文化遺産の問題を考えます。

-
【地球研】地球研×ナレッジキャピタル「おいしい地球環境学」 第1回「タンザニアでスパイスの村をつくろう-貧困問題と環境荒廃に向き合う知恵」
2017年11月24日タンザニア東部のウルグル山域は、過疎化の進む貧困地域です。急峻な地形での焼畑耕作が土壌の劣化や森林の消失を招いています。これは、典型的な「貧困と環境破壊の連鎖」です。本講座では、ウルグル山域の自然環境や在来農耕の知恵を活かし、バニラやクローブなどの香辛料作物の栽培を通じて「人びとの暮らしの向上と資源・生態環境の保全や修復を可能にする」取り組みを紹介します。また、タンザニアと日本の私たちをどうつなげるかを一緒に考えてみましょう。
-
【上智大学研究機構イスラーム研究センター主催シンポジウム】「中東イスラーム世界における都市空間」
2017年11月23日本シンポジウムは、大学共同利用機関法人・人間文化研究機構ネットワーク型基幹研究プロジェクト地域研究推進事業『現代中東地域研究』および、上智大学学術研究特別推進費重点領域研究「イスラームとキリスト教他諸宗教の対立・交流・融和の地域間比較研究」の研究成果です。

-
【民博】みんぱくゼミナール 「仮面の世界をさぐる―アフリカ、そしてミュージアム」
2017年11月18日私の、1975年に始まる、仮面をめぐる、日本で、アフリカで、そしてミュージアムでのフィールドワークの軌跡をつづり、仮面という装置の文化の違いを超えた成り立ちについての理解を得るまでのプロセスをたどります。

-
【日文研】第315回 日文研フォーラム「桂離宮の地霊(ゲニウス・ロキ)――近世の庭園における古代の神話と文化」
2017年11月14日桂の地は古代から、神話、民衆伝承、また中国文化に深く通じた日本の教養人の文化が集結し、混ざり合う場所であり、貴族たちは長くそれらを歌に詠むことで受け継いできました。
そうした桂の地霊―ゲニウス・ロキ―が持つ豊かな歴史なくして、八条宮智仁親王による桂離宮の景観設計は実現したでしょうか。宮は、保養地として名高いこの地の文化、そして、帝と朝廷が政治的にも、経済的にも、知的にもその威光を輝かすことのできた、過ぎ去った平安時 代の一端を、甦らせようとしたのではないでしょうか。
桂離宮の景観の独創性は、桂という土地にまつわる長い物語から始まります。
-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「娯楽の場としてのコーヒーハウス――イランのガフヴェ・ハーネ」
2017年11月12日イランのガフヴェ・ハーネ(ペルシア語で「コーヒーの家」)と呼ばれる伝統的な喫茶店は、かつて人びとが余暇を楽しんだ場でした。民衆の心躍らせた聖者、英雄、任侠者が活躍する語り物や、こうした物語の場面を描いたコーヒーハウス芸術などの娯楽文化を紹介します。

-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「心の扉を開ける鍵としてのコーヒー――パレスチナ・イスラエルでのフィールドワークから」
2017年11月12日10月22日は台風の影響に伴い延期となりましたので、下記日時にて開催します。
2017年11月12日(日)11:00~12:00アラブから世界に伝播したコーヒーは、今もアラブの食文化において重要な役割を果たしていますが、その飲み方や嗜好は時代とともに変遷しています。パレスチナ・イスラエルの事例から、中東におけるコーヒーの今をご紹介します。後半は新着資料展示「標交紀の咖啡の世界」のギャラリートーク。

-
国際シンポジウム「災害文化形成を担う 地域歴史資料学の確立をめざして」
2017年11月11日国際シンポジウム「災害文化形成を担う地域歴史資料学の確立をめざして」を神戸にて11月11日・12日に開催します。本シンポジウムでは、東日本大震災後の実践的研究を踏まえながら、国際的なネットワークに着目して、これからの地域歴史資料学を展開いたします。

-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「カザフの天幕――住居から祝祭の空間へ」
2017年11月05日中央アジアの広大な草原で移動式の住居として使われていた天幕は、カザフ遊牧民が定住化した現在では主に祝祭や儀礼のために使われるようになっています。天幕に反映された世界観や死生観、天幕の使用方法などをとおして、カザフ社会の変容を考えます。

-
【民博】みんぱくワールドシネマ「火の山のマリア」
2017年11月05日国立民族学博物館では2009年度から、研究者による解説付きの上映会「みんぱくワールドシネマ」を実施しています。9年目の今期からは<人類の未来>をキーワードに、映画上映を展開していきます。今回はグアテマラ・フランス合作「火の山のマリア」を上映します。グアテマラの高地に暮らす17歳のマヤ人のマリアの運命を通して、現代社会における先住民族マヤの問題を知りたいと思います。

-
【国文研】平成29年度「古典の日」講演会
2017年11月03日「古典の日」は、古典が我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、国民が広く古典に親しむことを目的として、平成24年3月に法制化されました。11月1日に定められたのは、我が国の代表的な古典作品である『源氏物語』の成立に関して、最も古い記述が寛弘五年(1008)11月1日であるためです。
日本古典文学の文献資料収集と研究を主事業とする国文学研究資料館も、「古典の日」の趣旨に賛同し、平成24年度から記念の講演会を催しております。古典に親しむ絶好の機会として、大勢の方にお出でいただくことを願っております。
-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「フィールドワークとケガ――ベトナム西北部調査より」
2017年10月29日初めての長期のフィールドワークに向かう、わくわくとどきどきの道すがら、バイクで転倒しました。足と心に傷を負い、足を引きずりながら、フィールドワークが始まりました。でも、ケガをしたことによって見えてくる社会や文化の局面もあるのではないでしょうか。

-
【日文研】日文研一般公開「日文研の30年」
2017年10月28日開催日時:10月28日(土)10:00~16:30
場所:国際日本文化研究センター〔京都市西京区〕(参加無料・申込不要)
国際日本文化研究センター(日文研)の研究活動をより広く一般の方々に知っていただくため、今年も土曜日に開催いたします。創立30周年を迎え、今年のテーマ「日文研の30年」に沿った講演、所蔵資料の展示、教員による施設案内やスタンプラリーなどさまざまなイベントを行います。