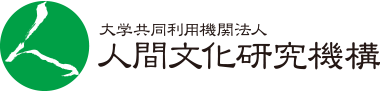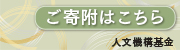イベント一覧
-
人間文化研究機構・味の素食の文化センター共催シンポジウム 「江戸の書物から読み解く庶民の食べ物と生活」
2018年01月19日町民文化が花開いた江戸時代。人々が口にしていた食材は実に豊かで、調理法は創意工夫と遊び心にあふれていました。江戸時代の料理書を紐解き、その豊かな食生活と生活文化、当時の知恵をみていきます。国文学研究資料館と味の素食の文化センターの連携によりデジタル化された江戸時代の料理書の数々もお楽しみください。

-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「トナカイの角」
2018年01月14日中国東北部・大興安嶺森林地帯ではトナカイの飼育を続ける人びとがいます。彼らはトナカイを屠殺することはなく、毎年生え替わる角を採取し、販売しています。本発表では、いまでも中国においてトナカイの飼育を続けることができる理由を解説します。

-
【現代中東地域研究】<上智大学拠点主催>映画“シリア・モナムール”上映会
2018年01月11日人間文化研究機構ネットワーク型基幹研究プロジェクト地域研究推進事業「現代中東地域研究」及び上智大学学術研究特別推進費重点領域研究「イスラームとキリスト教他諸宗教の対立・交流・融和の地域間比較研究」研究事業の一環として、2014年カンヌ国際映画祭で賞賛を浴び、2015年山形国際ドキュメンタリー映画祭でも、観客に深い衝撃を与えて《優秀賞》を受賞した『シリア・モナムール』の上映会を予定しています。

-
【日文研】第317回 日文研フォーラム「観音さまを抱きしめる―― 西国三十三所巡礼の旅」
2018年01月09日現代人は孤独である。それゆえに、たまには誰かとハグでもしたくなる。死に別れた父母、夫や妻、子ども、友人、知人などとは、なおさらである。そのために、人は西国三十三所巡礼の旅に出かけるのである。巡礼の旅では、念願の「観音さま」に出会う。ここで言う「観音さま」とは、恋しき人々の化身である。つまり観音像には、 死に別れた恋しき人々の面影が託されているのである。
本講演では、西国三十三所巡礼の旅に出る人々がそこに何を求めているのか、民俗学の立場から続けてきたフィールドワークに基づいて考察します。そして、私自身の巡礼の体験を、皆様と分かち合いたいと思っています。

-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「『数』をあらわす――音声言語と手話言語」
2018年01月07日数(かず)を表す表現に焦点をあて、前半は音声言語で1から10まで数えるときに同時につかう手の表現、後半は、世界のさまざまな手話言語の表現についてお話します。ジェスチャーと手話言語はどのように異なるのか、世界各国の言語の映像を見ながら説明します。

-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「みんぱくシンボルマークをえがく(再)」
2017年12月24日みんぱく開館40周年にあたる今年のわたしの話題は、「みんぱくシンボルマーク」です。このマークは一見単純そうな形に見えますが、実際にえがいてみると思わぬ発見がありました。そんなエピソードや、創設当時のマークの原版、リニューアルしたマークなどを見ながら、ふたたび、みんぱくシンボルマークに迫ります。

-
【地球研】第12回地球研国際シンポジウム Trans-scale Solutions for Sustainability
2017年12月20日In this symposium, we discuss new approaches towards a sustainable future, focusing on the conflicts of resources, values, and governances among stakeholders across time and space. Behind the current understanding of the local tragedy of commons there exist trans-spatial issues such as local, national and global scale conflicts/synergy, as well as trans-temporal issues encompassing past, present and future, which need to be identified and solved. Analysis of the conservation and development of natural, social and institutional capitals is key to new directions of research. In particular, water and water-related issues under the conditions of climate change and shortage of land will be highlighted with scenario developments, and with the use of integrated indices and socio-ecological-economic models
日本語ページ http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/symposiums/no12.html
English Page http://www.chikyu.ac.jp/rihn_e/events/symposiums/no12.html

-
【東北大学拠点・富山大学拠点シンポジウム】「環境から見る持続可能な経済発展」
2017年12月20日2015年に国連は「持続可能な開発目標(SDGs)」として17のグローバルロ標を制定しました。本シンポジウムは、Goa113とGoa115に含まれる「森林の持続可能な管理」および「気候変動とその影響」を主要なテーマとして開催するものです。
どなたでも自由にご参加いただけますが、事前登録フォームヘの登録をお願いしています。以下のリンク先から事前にお申込みください。本シンポジウムは人間文化研究機構ネットワーク型基幹研究プロジェクト「北東アジアにおける地域構造の変容:越境から考察する共生への道」の一環として開催するものです。

-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「目に見えない世界を歩く――「全盲」のフィールドワーク」
2017年12月17日本年12月、拙著『目に見えない世界を歩く』(平凡社新書)が刊行される予定です。新著の内容を紹介するとともに、視覚障害者が本を書く際の工夫などについてお話しします。「全盲」とは単なる障害ではなく、マジョリティと異なる生き方(行き方)をもたらす異文化です。ある全盲者の半生をいっしょにフィールドワークしてみましょう。

-
【民博】みんぱくゼミナール 「オラン・アスリの家族―母系制・妻方居住・一夫多妻」
2017年12月16日マレーシアの先住民オラン・アスリは、家族や親族の濃密なつながりの中で生きています。母系制や妻方居住、一夫多妻など、彼ら家族の特徴を紹介しながら、家族とは何かについて考えます。

-
【地球研】地球研×ナレッジキャピタル「おいしい地球環境学」 第3回「おいしい食の未来のカタチ -ブータンの有機農業政策の失敗(?)から考えてみよう-」
2017年12月12日私たちの食べ物はどこで、だれによって、どのようにつくられているのでしょうか?近年日本でも、オーガニックや有機野菜への関心が高まっていますが、その全容を知ることは難しいものです。健康的で地域文化に相応しく、環境に配慮し持続可能な方法で生産された食べものの確保を目的に、ブータンでは2007年より有機農業政策が作られました。その経験と農民の対応を踏まえ、私たちが望む「おいしい食の未来」について一緒に考えてみましょう。
-
【日文研】第316回 日文研フォーラム「『Japan Teaブランド』の構築――太平洋を渡った緑茶」
2017年12月12日明治時代、緑茶が日本の主力輸出商品であったことはよく知られています。実は、その八割はアメリカに輸出されていました。ちなみに、当時のアメリカでは主に緑茶が消費されていました。
本講演では、日本の商人たちがいかにしてアメリカ市場向けに「Japan Tea ブランド」を構築したか、その努力と挑戦の過程を考察します。
さらに、そのブランドは翻って、昭和初期の日本における緑茶の消費パターンに大きな影響を与えることになりました。その側面についてもご紹介したいと思います。

-
【日文研】第12回 日文研・アイハウス連携フォーラム「オーナメンタル・ディプロマシー: 明治天皇と近代日本の外交」
2017年12月08日近代日本の外交史の研究では、なぜ天皇の役割を取り上げず、明治天皇の研究も外交分野として扱わないのか。明治天皇を抜きにして近代日本の欧州・アジア諸国との外交関係を語れない、とブリーン教授は主張します。明治天皇は、権力関係の構築に欠かせないダイナミックな儀礼的役割を果たしました。なかでも注目すべきは、天皇による勲章の贈答儀礼です。天皇は欧州・アジアの君主・大統領から海外の勲章を受理し、日本の勲章を授与しました。こうした勲章の贈答は、君主間の関係を成立させる上で欠かせない戦略でした。
本プログラムでブリーン教授は、王政復古から日清戦争の勃発までの時期を視野に入れながら近代日本の勲章制度の成立や勲章贈答の葛藤に光をあてます。とりわけ日本とロシア、日本と朝鮮、日本とイギリスとの外交関係にみる勲章の役割を検討し、明治天皇が近代日本の外交関係において能動的な役目を果たしたことをお話しいただきます。
※発表・コメントについては英語のみ、質疑応答については日本語または英語 -
【地球研】地球研×ナレッジキャピタル「おいしい地球環境学」 第2回「荒廃泥炭地の回復にむけた挑戦」
2017年12月05日かつて、東南アジアに広く存在した熱帯泥炭湿地林は、1990年代以降、大規模に排水されてアカシアやアブラヤシが植栽されてきました。排水によって乾燥した泥炭地は、火災が生じやすく、煙害による健康被害や地球温暖化をもたらしています。私たちは、住民との間の徹底した討論や意見交換から、その解決方法を考え実践してきました。それは、地域の人々と一緒に乾燥した泥炭を湿地化し、そこで営む農林業(パルディカルチュア)を推し進める取り組みです。本講座では、湿地で栽培できるサゴヤシからとったデンプンもご覧いただきます。
-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「カナダ先住民の文化の力―過去、現在、未来」
2017年12月03日2017年7月1日にカナダは建国150周年を迎えます。カナダ先住民は、同国の先住民政策の影響を強く受けつつ、独自の文化を継承したり、新たに創りだしたりしてきました。多様なカナダ先住民文化の歴史と現状について、企画展示を見ながら紹介します。