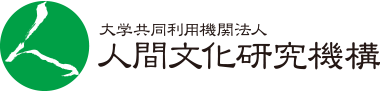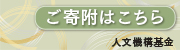イベント一覧
-
【日文研】第320回 日文研フォーラム「重々たる法界 目前に彰(あき)らかなり ―― 禅院の塔頭(たっちゅう)における「境致」の選定」
2018年04月10日中国の南宋(1127-1279年)五山では、禅院内外の建造物や自然物を禅宗的な観点で選定し、これを「境致」と言っていました。そして、多くの場合、十の重要なものを選んで「十境」と呼びます。これがやがて日本に伝えられ、中世の京都五山や鎌倉五山で行われるようになりました。
ただし、日本の五山における境致の選定は、禅院本寺だけにとどまらず、子院とも言える塔頭にも広がっていったのです。これは、境致選定の日本的展開であり、日本的特色とも言えましょう。
本講演では、日本の五山本寺による境致の導入を見たうえで、そのように塔頭で行われた境致選定の実態解明を試みたいと思います。

-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「田の神(タノカンサァ)」について
2018年04月01日全国に分布する田の神信仰のなかで、鹿児島県から宮崎県西部の一部の地域に分布する石で作られる田の神(タノカンサァ)は、南九州独特の文化として知られています。ここでは、展示しているタノカンサァを中心に、豊穣を願う田の神信仰について紹介します。

-
【地球研】第76回地球研市民セミナー「中国の環境問題と向き合って―風上・風下論を超えた環境協力の可能性」
2018年03月23日経済成長を続け、世界第2位の経済大国となった中国にとって、PM2.5(微小粒子状物質)に代表される大気汚染をはじめ、土壌、河川、湖沼の汚染などの環境問題は、大きな課題となっています。情報公開が十分ではない中で水質汚染、土壌汚染が深刻化した結果、住民の健康や食の安全に対して、中国の人々は、強い懸念を感じています。
一方で、 日中間では砂漠化防止の植林活動など様々な協力や取り組みがなされてきています。しかし、これまでは、どうも日本は自国の環境技術や省エネ技術が優れているという考えに縛られていて、中国の現実がうまく伝わっていないようにも見えます。
今回のセミナーでは、中国の研究者と共同して行ってきた水資源や砂漠化問題などの研究を紹介しながら、東アジアとも言うべき地域の国際協力の可能性を皆さんと考えます。

-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「博物館資料情報の再収集 EEM北米資料とソースコミュニティとの「再会」」
2018年03月18日約半世紀前に収集されたEEM資料(北米)は、現在でも物質的にはその姿をとどめている。収集者の日記や旅程から、収集の意図と来歴を辿ることも可能だ。ところが資料情報はほとんど残っていない。資料の文化的生命力の回復のために実施した、ソースコミュニティによる熟覧調査を紹介する。

-
【歴博】歴博映像フォーラム12「モノ語る人びと-津波被災地・気仙沼から」
2018年03月17日本年度の映像フォーラムでは、宮城県気仙沼市小々汐で被災した尾形家住宅を対象とした生活資料の救援活動を扱った民俗映像を紹介します。東北地方太平洋沖地震以降、宮城県気仙沼市小々汐の尾形家住宅を対象として生活資料の救援活動を続けてきました。
一般に、被災地域の資料を保全する文化財レスキュー活動では、どれだけの資料が保全できたのか、またどのような手順で保全をしたのかといった成果や手法に注目が集まります。一方で、この作品は、被災現場での生活資料の保全から洗浄、整理、保管に至る作業のなかで、生活資料の所有者やその家族、作業に携わる市民が、その過程をどのように経験し、そのなかで過去の生活とどのように向き合ってきたのかに注目します。そして作業の進展のなかで、人びとがモノや景観といった広い意味での物質文化を目の前にすることを通じて、過去の地域の生活を思い出して語る行為に注目しました。
東北地方太平洋沖地震による津波の被災地域は、現在、大規模な土地改変により過去の景観が失われ、経験を語る上で手がかりとなるものが消えつつあります。そのなかで、いかに過去と現在、そして未来を結んでいくのかをモノを通した語り、モノを語る行為に注目して紹介します。

-
【民博】みんぱくゼミナール 「万博資料収集団―太陽の塔に集った仮面、神像、なりわいの道具」
2018年03月17日大阪万博を2年後に控えた1968年、世界の諸民族の資料を収集するというミッションが若き人類学徒たちに与えられました。限られた予算と時間とのなかで世界に挑んだ「万博資料収集団」を紹介します。

-
【日文研】第66回 学術講演会「反転する井伊直弼―マッカーサーと大河ドラマのつながり」「パラオの女性首長が見た日本」
2018年03月16日講演Ⅰ「反転する井伊直弼―マッカーサーと大河ドラマのつながり」 石川 肇 国際日本文化研究センター 助教
開国の恩人か、はたまた志士を弾圧した非道の権力者か・・・。幕末の大老、井伊直弼の評価が見直されたのは戦後のことで、それ以前はまったくの悪役だった。では、なぜ見直されたのだろうか? その答えとしてNHK大河ドラマの第一作目となった舟橋聖一『花の生涯』の強い影響があったことは、その歴史をひも解けばわかる。が、そして実はその背後にマッカーサーがいたという、驚きの「占領物語」があったことを明らかにしたい。
講演Ⅱ「パラオの女性首長が見た日本」 安井 眞奈美 国際日本文化研究センター 教授
ミクロネシアのパラオ共和国は、人口2万人弱の島嶼国である。かつてパラオは、国際連盟によって南洋群島の委任統治を託された日本により、太平洋戦争終結の1945年まで統治された。その頃に幼少期を送り、のちにパラオの女性首長となる一人の女性は、母系社会の慣習を守り、また数多くの日本人と友人になって、戦後は日本にも訪れた。彼女の生涯を通じて、母系社会の慣習と変遷、パラオと日本の関係を見ていきたい。

-
【日文研】第319回 日文研フォーラム「明治の人々を科学に導いた福澤諭吉の絵入り教科書――『訓蒙窮理図解』をひもとく」
2018年03月13日明治時代の思想家にとって緊急の課題の一つは、西洋の力の背景にある近代科学を、いかに受容し、これに対応するかでした。そうした中でも、明治元(1868)年に福澤諭吉が刊行した絵入り教科書『訓蒙窮理図解』は、一般民衆を対象に、科学の知識を原理から易しく伝えることを目的としていました。
本講演では、この書の特徴を明らかにするために、福澤が基にした西洋の科学書、また日本で同時代に出版された他の科学書と対比しながら紹介します。ここから、明治維新後の社会において、子供を含む一般の人々への科学主義の普及を重要視した、福澤の独自性や新規性を考えてみたいと思います。

-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「特別展『太陽の塔からみんぱくへ』――東南アジアを中心に」
2018年03月11日いまから50年前、大阪万博の太陽の塔内で展示する民族資料を集めるために、20名弱の若手研究者からなる収集団が結成されました。彼らの収集は、その後、みんぱくの設立にもつながります。東南アジアを中心に、収集団の活動について、特別展をみながら紹介します。

-
【民博】みんぱくワールドシネマ「ディーパンの闘い」
2018年03月10日国立民族学博物館では2009年度から、研究者による解説付きの上映会「みんぱくワールドシネマ」を実施しています。9年目の今期は<人類の未来>をキーワードに、映画上映を展開しています。今回はフランス映画「ディーパンの闘い」を上映します。戦火のスリランカから逃れ、フランスで新しい生活を始めた“偽装家族”を通して、難民の状況について考えたいと思います。

-
大手町アカデミア × 人間文化研究機構 無料特別講座のご案内
2018年03月08日人間文化研究機構(以下「人文機構」)は、「大手町アカデミア」(主催:読売新聞東京本社 運営協力:中央公論新社)と連携・協力の下、人文機構が、平成28年度から推進しています基幹研究プロジェクトの成果発表の一環として、広く一般を対象に、無料特別講座を実施します。
今回の講座は、17の基幹研究プロジェクトの中から、2プロジェクトの研究成果を発表するとともに、硬派の歴史書としては異例のベストセラーとなった『 応仁の乱 』の著者 呉座勇一国際日本文化研究センター助教とともにお伝えしていきます。ぜひお申し込みください。
日 時:平成30年3月8日(木)19:00~(18:30開場)[定員100名]
場 所:読売新聞ビル3階「新聞教室」(千代田区大手町1-7-1)
プログラム:
【第1部】
○オランダの史料から読み解く「家康の知られざる外交術」
講師 :フレデリック・クレインス (国際日本文化研究センター 准教授)
【第2部】
○バチカン図書館で発見された「世界的記憶資産・キリシタン文書」
講師 :大友 一雄 (国文学研究資料館 教授)
○ナビゲーター:呉座 勇一 (国際日本文化研究センター 助教)
無料特別講座の詳細及びお申し込みはこちらをご覧ください(外部サイトにリンクします)
【2/13 追記】おかげさまをもちまして、応募定員に達しました。なお、空席が生じた場合には、リンク先で自動的に受付が開始されますので、受付状況は随時ご確認ください。

-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「イスラーム教育における音と文字」
2018年03月04日イスラーム教育の基礎は原典の暗記にあります。聖典クルアーンに始まり、預言者ムハンマドの言行録(ハディース)にうつります。エジプトでは暗記中心の学校教育が批判されて久しいのに対し、一般の信徒であっても原典の音に親しむことが重視されている理由を探ります。

-
第32回人文機構シンポジウム 「人文知による情報と知の体系化~異分野融合で何をつくるか~」(機構合同シンポジウム)
2018年02月26日データから情報へ。情報から知へ。知の触発によって見えるものは何か。大学共同利用機関法人である人間文化研究機構と情報・システム研究機構は、これまで、両機構の連携・協力による共同研究を行ってまいりました。
本年度、両機構は、連携・協力推進に関する協定を締結し、文理融合研究をさらに進めていくことを確認いたしました。今回の連携・協力推進協定締結を機に、さらに新たな知の創造、異分野融合の促進、新領域の創出を推進してまいります。
本シンポジウムによって、両機構が、文と理にまたがる多様な分野で、興味深い、先進的な研究に取り組んでいることを実感していただきたいと思います。多数の皆さまのご来場をお待ちしております。

-
【地球研】第21回地球研地域連携セミナー(滋賀)地域の底ヂカラ 結(ゆい)の精神が育むいきものの多様性
2018年02月24日甲賀の大地に広がる古琵琶湖の肥沃な土壌は豊かな自然や生きものを育み、伝統的な生業や文化を培ってきました。しかし、中山間地域では、農家の減少や高齢化、後継者不足が進み、耕作放棄地がみられるなど、集落の存続が懸念されています。さらに、里山などの身近な自然環境にも人の手が入らなくなるため荒廃が進み、かつてみられた生き物のにぎわいも少なくなっています。
本セミナーでは、身近な自然の価値に共感・共鳴し、その恵みを将来の担い手に受け継いでいくために、結の精神で集落をまとめ、農業の6次産業化や、豊かな生き物を育む水田作りに取り組む甲賀の小佐治地区の事例を紹介しながら、中山間地の農業・農村集落の未来について皆さんとともに考えます。

-
国際シンポジウム「近世都市の常態と非常態ー水路・川・洪水ー」
2018年02月24日人間文化研究機構 広領域連携型基幹研究プロジェクト「日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築」国文学研究資料館ユニット「人命環境アーカイブズの過去・現在・未来に関する双方向的研究」が主催する国際シンポジウムです。2016年2月には東京(立川)でプレ研究会を開き、ロンドン・イスタンブル・北京・江戸における災害の概況と研究状況の相互理解を図りました。
同年11月にはロンドン大学歴史学研究所で開催された「都市と災害―歴史における都市の適応能力とレジエンス」において第7セクション「近世首都における災害対応」を持ち、首都であることによる災害対応の共通性、災害後の秩序維持問題の差異性が議論されました。
今回は、これらの活動を受けて、「近世都市の常態と非常態―水路・川・洪水―」をテーマに2017年度国際シンポジウムを開催いたします。