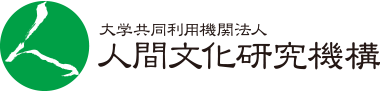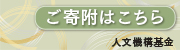イベント一覧
-
割り切れない「男」と「女」の問題~文化×科学×社会からみなおす、ひとの性差~
2019年03月24日
-
第35回人文機構シンポジウム レクチャーコンサート 「中東と日本をつなぐ音の道(サウンドロード)―音楽から地球社会の共生を考える」
2019年03月23日 -
トークセッション「のぞいてみよう! 土・ミツバチ・食の世界~持続可能な社会を目指して」
2019年03月16日 -
【地球研】第79 回地球研市民セミナー「インドネシアの泥炭開発・環境問題―日本(加工貿易国)とインドネシア(資源国)の関係」
2019年03月12日日 時:2019 年3 月12 日(火)18:30-20:00(18:00 開場)
会 場:ハートピア京都 3 階大会議室
聴 講:無料 / 定 員:200 名(申込先着順)
概 要:
インドネシアでは1985 年ごろよりアブラヤシの植栽が大規模に行われ、それはこの地域に存在する熱帯泥炭地にも爆発的に拡大しました。
インドネシア国土の8%を占める泥炭地はそれまで泥炭湿地林として存在してきましたが、この大規模開発により乾燥化・劣化が進み、1990 年代末より大規模な火災が発生するようになりました。私たちはこの荒廃した泥炭地の回復をインドネシア地域の人々と手を取り合いながら実施しています。
一方、この泥炭地の荒廃問題から、インドネシアの資源輸出国としての問題が見えてきます。今日、これらの大規模な植栽と輸出の急増は、森林減少、泥炭火災などの問題のみならず、インドネシア製造業の停滞にもつながっています。このようなインドネシアの資源国としての展開と表裏の関係になるのが加工貿易を柱としてきた日本の製造業の発展です。
講演では、インドネシアの泥炭環境問題、泥炭地において生産されるアブラヤシの輸出と日本への輸入、さらに資源国としてのインドネシアの特質と問題点、それと表裏の関係にある日本の加工貿易国としての特質と問題点、そしてその解決の方策について考えます。
-
【日文研】第327回 日文研フォーラム「近代中国革命の思想的起源―日本からの建国思想の受容を中心に」
2019年03月12日清朝(1616-1912)はどのように崩壊したのか。従来の財政史・経済史とは異なる、東アジア内部の文化交流史という視点から、清朝の政治的正統性が切り崩されていく過程を辿ります。はじめに、親民説の台頭、次に、徂徠学の伝播とその意味、華夷思想の反転、そして最後に、最高権力の実態に対する再認識という四つの側面から考察を進めたいと思います。
近代中国革命は、まず明治天皇のような政治的権威を創出しなければならなかった。日本は、いわば近代中国革命の出発点なのです。

-
【日文研】第67回 学術講演会「子どもをめぐるグラフィックデザイン―日本の洋菓子広告をてがかりに」「京都の尼僧像にそそぐ光明―尼門跡寺院の新たな歴史をひらく」
2019年03月08日講演Ⅰ「子どもをめぐるグラフィックデザイン―日本の洋菓子広告をてがかりに」
前川 志織 国際日本文化研究センター 特任助教明治維新後の日本では文明開化の風潮のもと、砂糖・バター・ミルクを原料とする洋菓子が欧米から流入した。やがて洋菓子商品の大量消費を促すための広告活動が、マス・メディアを通して活発化する。それらの広告から、この商品が子どもとの結びつきを強めていったさまがみてとれる。キャラメルの新聞広告を中心に、広告と子どもとの結びつきについて、商品の文化的・社会的意味を形成する広告のデザイン表現に注目し考察したい。
講演Ⅱ「京都の尼僧像にそそぐ光明―尼門跡寺院の新たな歴史をひらく」
パトリシア・フィスター 国際日本文化研究センター 教授本講演では、京都の旧比丘尼御所や菩提寺に残された尼僧の肖像について紹介する。太閤秀吉の姉君を開山とする瑞龍寺は、比丘尼御所の中でも比較的豊かな寺院であったが、十八世紀の都の大火でほぼ焼失した。幸い菩提寺の善正寺に瑞龍寺関係の資料や貴重な品が残され、それらから開山日秀尼の生涯や、当時の法華宗の信仰など、知られざる歴史をたどることができる。またあわせて、宝鏡寺門跡の江戸時代の歴代住持や、菩提寺の眞如寺に安置されている4躰の尼僧の肖像彫刻についても述べる。経年劣化のひどかった御像を製作時の美しい姿に戻すべく修復を行った5年の間に、墨書や像内物などが発見され、新事実が浮かび上がってきた。
発表は日本語のみ

-
【歴博】歴博映像フォーラム13「二五穴-水と米を巡る人びとの過去・現在・未来-」
2019年03月02日「二五穴」は千葉県房総丘陵の小櫃川(おびつがわ)周辺に作られたトンネル状の用水路で、トンネルの大きさが「二尺五尺」(およそ60cm×150cm)であることから「二五穴」と呼ばれます。江戸時代の終わり頃から作られ始め、現在も利用されています。ひとつのトンネルは、長いもので200~700mあり、全てのトンネルをつなぐと、全長は10kmにもなります。歴博では、研究プロジェクト「日本の中山間地域における人と自然の文化誌」(H23-25年度)を立ち上げて、近世史(文献)・民俗学・生態人類学・生物学・地質学・考古学などの多様な研究分野による研究者で、二五穴について調査をおこなってきました。その成果は、これまでも展示・講演会・論文・エッセイなどで発信してきました。しかしそれだけでは、研究者・調査者の一方的な情報提供に偏ってしまいます。地域の未来を担う人々に研究成果を活用してもらうには、どうしたらよいのでしょうか。私たちは地域の歴史を残すために、地域の人びととの「協働」作業として映像を制作できないだろうかと考え、二五穴についての研究映像を制作することにしました。本フォーラムでは、二五穴について異なる視点から制作した2種類の映像を上映し、映像が、地域の記憶と思いと期待を紡ぎ、地域力、地元力を育む力になりうるか、考えてみたいと思います。
-
【日文研】第16 回 日文研・アイハウス連携フォーラム「明治日本オリンピック事始め~スポーツ文明論試論」
2019年02月20日幕末に欧米列強と不平等な条約を結んだ日本。その後、領事裁判権の撤廃、北清事変への列強との共同出兵、日英同盟の締結、対露戦の勝利、関税自主権の回復等により、建前上は「文明国=一等国」となったものの、形式上の「対等」と実際の「対等」は別、というのが国際社会の厳しい現実でした。「新参者」日本が国際社会で対等を獲得できる場が存在したとすれば、それは同一ルールが適用されるスポーツの場、その頂点に立つオリンピックという舞台でした。近代オリンピックへの参加こそ、世界の「文明国」の仲間入りを果たした証しと考えることができます。本講演では、日本の1912 年ストックホルム大会参加への道程を文明の視点から考察します。
*発表は日本語のみ
-
第14回人間文化研究情報資源共有化研究会
2019年02月15日人間文化研究機構において第 3 期の nihuINT が公開されて、2 年が経過した。人文学の研究データ を取り巻く状況は、データ基盤の整備状況や、オープンデータの動向、人文学の「危機」といった議論 を含め、大きく変化しつつある。そのような状況の中で、人間文化研究機構が持つべきデータ、持つべ きシステムとはどのようなものであるべきか、次のステップのための議論をさらに深めなければならな い。本研究会では、nihuINT のありようそのものから含め、「ゼロベース」での議論を行い、人間文化 研究機構のみならず、人文学が持つデータの形式・保持方法・利用方法などについて、様々な見地から 検討したい。
〇 日 時 平成31年2月15日(金)13 時 30 分~16 時 30 分(13:00 開場)
〇 会 場 大阪大学中之島センター( 507 講義室 )
大阪市北区中之島 4-3-53
-
【日文研】第326回 日文研フォーラム「古代日本の国際交流における動物の贈答―ラクダ・羊を中心に」
2019年02月12日古代日本の国際交流では、しばしば動物の贈答が行われました。文献史料によれば、六世紀から十二世紀にかけては、中国や朝鮮半島から日本列島にもたらされた舶来動物は、馬・ラクダ・ロバ・ラバ・羊・クジャク・オウム・犬・ガチョウ・黑猫など多種多様でしたが、日本列島からの舶出動物の種類は主に馬・牛でした。
本発表では、ラクダや羊の贈答を中心に取り上げ、贈与側の意図や、受け取った日本側の対応を検討しながら、東アジアの国際交流において動物が果たした役割を捉えてみたいと思います。

-
国際シンポジウム「国際海洋都市平戸と異文化へのあこがれ―在外資料が変える日本研究」
2019年02月09日2019(平成 31)年 2 月 9 日(土)、国際シンポジウム「国際海洋都市平戸と異文化へのあこがれ―在外資料が変える日本研究」が、長崎県平戸市の平戸オランダ商館において開催されます。
本シンポジウムは、平戸市及び(公財)松浦史料博物館の全面的なご協力をいただき、人間文化研究機構ネットワーク型基幹研究プロジェクト「日本関連在外資料調査研究・活用事業」の中間的な成果を、研究者や社会一般、とりわけ歴史的に縁の深い、平戸において皆様にご披露する重要な機会です。
「日本関連在外資料調査研究・活用事業」では、とりわけ国際日本文化研究センターにおいて、「ハーグ国立文書館所蔵平戸オランダ商館文書調査研究・活用」、通称「平戸班」が、平戸オランダ商館旧蔵の、オランダ商館長未刊行書簡などの調査研究および活用をすすめております。
本シンポジウムでは、平戸オランダ商館文書をふくめ、この時期の日欧交流研究の泰斗、京都大学名誉教授、松田清先生をご招待してご講演をいただく予定です。また、オランダ・ハーグ文書館に保存されてきた、平戸関係文書の解読をすすめてこられた、フレデリック・クレインス先生、ライデン大学のシンシア・フィアレ先生から詳しい報告をいただきます。
そのほか、大分でのキリシタン弾圧や宗門人別改め関連文書の収集であるマレガ文書については、京都外国語大学のシルヴィオ・ヴィータ教授からの報告、歴博の福岡万里子准教授より、一昨年、全国を巡回したシーボルトの遺品復元の展覧会に関連する報告、国語研の朝日祥之准教授より、在外資料がもたらす海外への人の移動史の精緻化についての報告、日文研の根川幸男機関研究員より、平戸出身の実業家・山縣勇三郎のブラジルでの活躍についての報告などがあり、充実した日程を予定しております。

-
大手町アカデミア× 人間文化研究機構【無料特別講座】「世界から方言が消えたなら?-知られざる『弱小言語』の魅力」
2019年02月07日人間文化研究機構(以下「人文機構」)は、「大手町アカデミア」(主催:読売新聞東京本社運営協力:中央公論新社)と連携・協力の下、人文機構が平成28 年度から推進しています基幹研究プロジェクトの成果発表の一環として、広く一般を対象に、無料特別講座を実施します。講座の概要・申込方法等は以下をご参照の上、ぜひお申し込みください。
講 師:木部 暢子(国立国語研究所教授・副所長)
ナビゲーター:ロバート キャンベル(国文学研究資料館長)
日 時:2019 年2 月7 日(木)19 時~20 時45 分(開場18 時30 分)
会 場:読売新聞ビル3 階「新聞教室」(東京都千代田区大手町1-7-1)
受講料:無料
定 員:100 名(定員に達し次第締め切ります)
-
【日文研】第325回 日文研フォーラム「猫鬼の話―お伽草子『酒呑童子』と近世のパロディー絵巻」
2019年01月11日中世後期・近世初期の読み物としてのお伽草子の中では、鬼と英雄譚の『酒呑童子』ほど人気があり、数多く模写されたものはないでしょう。本発表では、鬼の酒呑童子の歴史的描写と魅力、そして16、17世紀の読者の享受について考察したいと思います。
さらに、近年アメリカで発見された18世紀のパロディー作品、『鼠乃大江山絵巻』を取り上げて分析してまいります。戯画で知られる英一蝶作かと思われ、鬼を猫に、人間の勇士を鼠に描き、皮肉的でとてもチャーミングな絵巻です。
-
【地球研】第26回地球研地域連携セミナー(大阪)「私たちの祖先は気候変動にいかに対峙してきたか ―弥生時代から近世まで―」
2018年12月16日日 時:2018年12月16日(日)13:00-16:45(開場12:30)
会 場:大阪歴史博物館 4階講堂概 要:
近年、大阪周辺でも集中豪雨や台風などによる被害が頻発していますが、私たちはそうした気象・気候災害にどのように対応していけるでしょうか。
総合地球環境学研究所(地球研)の気候適応史プロジェクトでは、樹木年輪の酸素同位体比などの最新の古気候データを、さまざまな考古資料や文献史料と照合することで、弥生時代以来の日本史の多くの時代に起きた気候の変動に対して、私たちの先祖が繰り広げた格闘の歴史を明らかにしてきました。
今回のシンポジウムでは、大阪の歴史情報の発信拠点である大阪歴史博物館において、祖先が私たちに残してくれた教訓を、皆さんと共に分かち合いたいと思います。
-
【地球研】第10回地球研東京セミナー「地球環境と生活文化――人新世における学び」
2018年12月15日日 時:2018年12月15日(土) 13:00 - 17:00
場 所:東京大学駒場キャンパス アドミニストレーション棟3階 学際交流ホール
参 加:入場無料・申込不要概 要:
「私たちが知的に重視するもの、忠実さ、愛情や信念が内側から変わらずして、倫理観が転換したことなどなかった」―環境倫理学者アルド・レオポルドの言葉です。
作られた物を消費する力から、既にある物を探し出す力へ。私たちが価値を置く力が変わるとき、私たちの倫理観にもきっと大きな変化が訪れるはず。物事は今より少しゆっくりと進むでしょう。そこにあるのは、速度を落とす中で気づくことに価値が置かれる未来です。
日々の暮らしも、デザインも、私たちはしばしば、その答えを「シンプルさ」に求めます。
しかし、倫理観に変化が訪れた未来を構想するには、「シンプルに生きるとはどういうことか」をも問わねばならないでしょう。この問いを深めるべく、本セミナーでは、無印良品の商品開発に携わってきた矢野直子さんと、哲学者鞍田崇さんによる講演と対話、大学院生や研究者による研究成果のポスター発表を行います。これらを通して、日常の中の様々な気づきと地球規模の環境問題とをつなぐものとは何かを、皆で考えてみませんか。