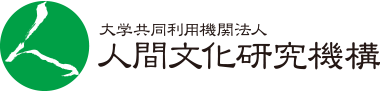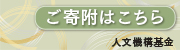イベント一覧
-
大手町アカデミア× 人間文化研究機構 無料特別講座のご案内「漆(japan)から日本史が見える―『シーボルトの日本コレクション』を中心に」
2018年12月14日人間文化研究機構(以下「人文機構」)は、「大手町アカデミア」(主催:読売新聞東京本社運営協力:中央公論新社)と連携・協力の下、人文機構が、平成28 年度から推進しています基幹研究プロジェクトの成果発表の一環として、広く一般を対象に、無料特別講座を実施します。
講 師:日高 薫 教授 (国立歴史民俗博物館)
ナビゲーター:倉本 一宏 教授(国際日本文化研究センター)
日 時:2018 年12 月14 日(金)19 時~20 時45 分(開場18 時30 分)
会 場:読売新聞ビル3 階新聞教室(東京都千代田区大手町1-7-1)
受講料:無料
定 員:100 名(定員に達し次第締め切ります)
-
【地球研】第13 回地球研国際シンポジウム “Humanities on the Ground: Confronting the Anthropocene in Asia”
2018年12月13日日 時:2018 年12 月13 日(木)- 14 日(金)
場 所:総合地球環境学研究所 講演室
参加ご希望の方は地球研HP 記載のメールアドレスに以下の項目を記載してお問い合わせください。
1.名前・メールアドレス
2.所属先・職名
3.参加希望日
4.昼食(お弁当) 希望あり/なし ¥1,000 程度
-
【日文研】第15回日文研・アイハウス連携フォーラム「『現代用語の基礎知識』からみた戦後日本の「宗教史」」(開催地:東京)
2018年12月05日晩秋になると書店の店頭に山積みにされる『現代用語の基礎知識』(自由国民社)は、戦後間もない1948年の創刊以来、途切れることなく毎年刊行されてきた息の長い現代語の事典で、最新号では113のジャンルに関連する基本語に加え、マスコミなどを通じて登場する新語や流行語の解説が収められています。本講演では、毎年の取捨選択を経て『現代用語の基礎知識』を構成してきた用語を、その時代の社会的関心を敏感に反映した“指標”と見なし、宗教関連用語を整理します。その上で、70年にわたって取り上げられてきた宗教関連用語の変遷から、戦後日本の「宗教史」について考えます。
*発表は日本語のみ
-
味の素食の文化センター・人間文化研究機構 共催シンポジウム 「地域と都市が創る新しい食文化」
2018年12月04日2013年の和食のユネスコ無形文化遺産登録、2020年東京オリンピックに向けたインバウンド増大等国内外の動向を受け、「食」への関心は、味や栄養面にとどまらず、食材を育む自然環境との調和、調理や作法を含む伝統性、さらにはそれらを包含する地域そのものの魅力へと広がってきています。
本シンポジウムでは、生産者、消費者、研究者、行政が一体となった、地域の食文化を活かした地域再生の取組みを紹介するとともに、グローバル化する社会において、地域と都市を繋ぎながらさらに豊かなくらしを育む発展のありよう、そしてひとりひとりが参加して創る新たな食文化について考えます。日 時:2018年12月4日(火)13:30~16:30
会 場:味の素グループ高輪研修センター大講義室
-
【地球研】第25 回地球研地域連携セミナー(滋賀)「地域のにぎわいと湖国の未来 魚のゆりかご水田~5 つの恵み~」
2018年12月02日広大なびわ湖を取りまく水郷では、人と自然の共生の営みが育まれてきました。田植えの季節、魚たちは湖から産卵に訪れ、田んぼは人と生きもののにぎわいであふれていました。びわ湖の固有種・ニゴロブナとお米からつくられる「ふなずし」は、湖と大地の恵みがおりなす湖国の伝統的な食文化として、今日まで受け継がれてきました。湖辺で進められた農業の近代化は、農業者の負担を減らし、生産性を向上しました。
しかし、その一方で、かけがえのない恵みが水郷から失われつつあることに心配の声も聞こえてきます。
本セミナーでは、湖と田んぼをつなぐ「魚のゆりかご水田」の取り組み、そして、湖を回遊するニゴロブナの母田回帰(自分の生まれた田んぼに帰ってくる習性)の発見に焦点をあてながら、「魚のゆりかご水田」がもたらす5つの恵み~生きもの・環境・子ども・農業・地域への恵み~をテーマに参加者の皆さんと対話を試みます。地域のにぎわいを取りもどすために、この活動の輪を広げ、湖国の未来をつむぐアイデアについて語り合いましょう!
-
【地球研】第24 回地球研地域連携セミナー(日之影)「未来への遺産-これからの日之影の人と自然-」
2018年11月23日2015年12月。国連食糧農業機関の世界農業遺産に、高千穂郷・椎葉山地域が認定されました。そして2017年6月、祖母・傾・大崩山系がユネスコ・エコパークに登録されました。どちらも、地域のこれまでの人と自然の関係に世界が注目した結果です。
大切なのはこれから。先人たちが長い年月をかけて積み重ねてきた農業システム、あるいは人と自然がともにある生き様。この遺産をどのように将来に活かすか、一緒に考えて行ければと思います。
-
【日文研】日文研一般公開「京都と時代劇」
2018年11月23日開催日時:11月23日(金・祝)10:00~16:00
場所:国際日本文化研究センター〔京都市西京区〕(参加無料・申込不要)
国際日本文化研究センター(日文研)の研究活動をより広く一般の方々に知っていただくため、今年も一般公開を開催いたします。今年は東映太秦映画村及び長岡京市ともタイアップし、テーマ「京都と時代劇」に沿ったさまざまなイベントを用意しております。

-
第 5 回全国史料ネット研究交流集会
2018年11月17日日 時:2018年11月17日(土)13:00~17:45
2018年11月18日(日)10:30~13:00会 場:新潟大学中央図書館ライブラリーホール
(新潟県西区五十嵐2の町8050番地)主 催:第5回全国史料ネット研究交流集会実行委員会
大学共同利用機関法人 人間文化研究機構(基盤機関:国立歴史民俗博物館)
-
第34回人文機構シンポジウム 国際シンポジウム「市民とともに地域を学ぶ-日本と台湾にみる地域文化の活用術」
2018年11月10日 -
【地球研】第23 回地球研地域連携セミナー(京都)ミツバチと共に未来をつくる ~ミツバチに優しいまちづくり・私たちにできること~
2018年11月04日地球研地域連携セミナーは、世界や日本の各地域で共通する地球環境問題の根底を探り、解決のための方法を考えていくことを目的に、地元の大学や研究機関、行政機関などと連携して開催するセミナーです。第23回となる今回は、京都市にて開催いたします。

-
第33回人文機構シンポジウム 鹿児島大学・人間文化研究機構協定締結記念シンポジウム 「鹿児島の歴史再発見-新しい地域文化像を求めて-」
2018年09月29日 -
【日文研】第323回日文研フォーラム「日本と韓国における「災難文学」の比較とその文化的背景」
2018年09月11日日本では地震や津波、火山噴火など自然災害の経験や被害を描く、いわゆる「震災文学」が前近代から綿々と創作されています。韓国では2014年4月に仁川と済州島を結ぶ大型旅客船の沈没という惨事をとおして「災難文学」という文学ジャンルが新たに認識されるようになりました。現代社会の災害・災難は単に自然災害だけではなく、近代文明の高度化が進むに従ってその多様性を増し続けています。
本発表ではこのような災難現象を描いた文学を「災難文学」と捉えて日・韓の災難に関する文学を比較することで、その文学に潜む両国の文化的な特徴を検討します。
-
【歴博】歴博映像祭Ⅱ「民俗研究映像の30年」
2018年08月18日1988年に始まった民俗研究映像の制作から30年を迎えるにあたり、これまでに制作した研究映像を網羅的に上映し、研究映像制作の当初のねらい、地域社会・民俗文化・映像制作技術等の変化などの視点から映像をよみとき、映像の蓄積による成果をひろく社会に還元します。
-
【国文研】中高生向け講演会「図書館で!ネットで!楽しい古典籍―おいしい江戸料理本の世界」
2018年08月02日日時 2018年8月2日(木)14時~16時(13時30分受付開始) 講師 山本和明氏(国文学研究資料館古典籍共同研究事業センター副センター長・特任教授) 場所 国際子ども図書館 アーチ棟1階研修室1 [ACCESS] 対象 中学生・高校生
※中高生向けの内容ですが、中高生以上の年代の方にお申込みいただけます。定員 70名 申込方法 ※事前の申込み受付は終了しました。中高生の方のみ当日の参加を受付けます。 その他 - 開始時刻までにアーチ棟1階 研修室1にお集まりください。
- 当日は、記録・広報用に撮影をさせていただきます。あらかじめご了承ください。
参加料 無料 
-
くらしの植物苑 特別企画「伝統の朝顔」
2018年07月31日江戸時代以降の独創的な知識と技術を駆使してつくり上げられた伝統の朝顔を広く知っていただき、人と植物との関わりを見るべく、本館では1999年以降、歴史資料としてこれらの朝顔を展示しております。