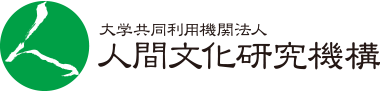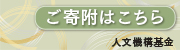イベント一覧
-
【民博】カナダ先住民のアートを作ろう
2017年10月01日2017年10月22日カナダのイヌイットや北西海岸に住む先住民の文化にふれるワークショップを開催します。
カナダ先住民の歴史や文化についてのお話を聞いて、企画展を見学した後、ワタリガラスの仮面や、イヌイットのステンシル版画を作りましょう!
-
【民博】みんぱくゼミナール 「ジョージ・ブラウン・コレクションの軌跡をたどる」
2017年10月21日みんぱくが所蔵するジョージ・ブラウン・コレクションをめぐる遺族の葛藤、所蔵博物館の危機、コレクションの転売・分散、そして新たなプロジェクトなど、約100年の歴史についてお話しします。

-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「ペルーの文化遺産を守る」
2017年10月15日南米アンデス文明の遺跡は、人口増や都市化の影響で破壊が進んでおり、保存は容易ではありません。日本調査団は、これまで文化遺産周辺で暮らす人々と協働でこれに対処してきました。今回は、近年調査しているペルー北高地パコパンパ遺跡における活動を紹介します。

-
【民博】台湾映画鑑賞会 映画から台湾を知る「祝宴!シェフ」
2017年10月14日多民族社会の台湾では、民族や地域ごとに特徴のある料理を楽しむことができます。オーストロネシア系の先住民族である原住民族、早い時期に台湾に移住し根をおろした福建系漢族や客家、第二次世界大戦後に移住をした中国大陸各地の人びとが豊かな食文化を育んできました。それぞれの食文化に深くかかわる料理では、味はもちろんのこと、ともに食べる時間も楽しみを与えてくれます。美味しいものをともに食べるという行為は、社会の中の絆をむすび、強くします。今回の映画会では料理を通して、社会のありかたを考えてみます。

-
【地球研】第20回地球研地域連携セミナー(椎葉村)世界農業遺産椎葉村シンポジウム
2017年10月12日地球研地域連携セミナーは、世界や日本の各地域で共通する地球環境問題の根底を探り、解決のための方法を考えていくことを目的に、地元の大学や研究機関、行政機関などと連携して開催するセミナーです。第20回となる今回は、宮崎県椎葉村にて開催いたします。

-
【日文研】第314回 日文研フォーラム「日本とベトナムのコミュニケーション文化――「出会い」と「別れ」の挨拶、「ほめ」と「断り」の発話行為を中心に」
2017年10月10日各民族や各文化コミュニティーが有している言語的な特徴は、その民族の文化・社会規範や行動習慣によって左右されます。文化的な背景が異なる話者が異文化間コミュニケーションを行うとき、その誤解により、文化ショック(culture shock)や文化衝突(culture conflicts)を引き起こすこともあるかもしれません。そのため、各国のコミュニケーション文化の特徴を比較しながら、それらの相違点と類似点を明らかにすることは、異文化間コミュニケーションにおける衝突を避けるのに必要不可欠であると考えられます。
本講演では、日本語とベトナム語の挨拶、また、「ほめ」や「断り」の発話行為に見られる言語的な特徴を検討します。両語の間には、驚くほど類似する点もあり、もちろん大きな相違もあります。ここから、日本人とベトナム人がこれらの行為を行う際のストラテジーや、それを支配するコミュニケーション文化の特徴を明らかにすることを試みます。
-
【民博】標交紀の咖啡とは?
2017年10月09日標交紀(しめぎゆきとし)の数少ない弟子のひとり、門脇祐希氏を講師にお迎えして、標の生涯と世界各地のコーヒー文化について本館教員とトークをおこないます。
また、当日は標直伝の咖啡の試飲(別途事前申込必要です。)もおこないます。
-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「島に住む人類」
2017年10月08日オセアニアの楽園環境は、人類が作り出したものである。本来は食用資源が貧弱だった島に、タロイモやパンノキなどを移植し、年間を通じて食糧が確保できる環境へと作り変えた。収穫のない季節を乗り切る方法など、島環境にすむ人類の知恵と工夫を紹介する。

-
大学共同利用機関シンポジウム2017 「研究者に会いに行こう!大学共同利用機関博覧会」
2017年10月08日日本を代表する研究機関・施設の活動をトークとブース展示でご紹介します。
★南極昭和基地とのLIVE中継あります。(15:00頃から)- 場所:@アキバ・スクエア(秋葉原UDX 2階)
アクセスマップ - 一般公開(参加無料/申込不要)
- 主催:大学共同利用機関協議会、大学共同利用機関法人機構長会議
- 後援:文部科学省

- 場所:@アキバ・スクエア(秋葉原UDX 2階)
-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「1962年、世界をめぐる旅」
2017年10月01日展示場にある絵画「朝陽アンコール」の作者・大熊峻は、1962年、伊谷賢蔵画伯と共に、中南米とヨーロッパを旅しました。後に世界遺産に登録された美しい町並みや建築物などの写真やスケッチ、そして旅日記を振り返りながら、当時の世界に思いを馳せたいと思います。

-
【民博】カナダ先住民のアートを作ろう
2017年10月01日2017年10月22日カナダのイヌイットや北西海岸に住む先住民の文化にふれるワークショップを開催します。
カナダ先住民の歴史や文化についてのお話を聞いて、企画展を見学した後、ワタリガラスの仮面や、イヌイットのステンシル版画を作りましょう!
-
【日文研】第65回 学術講演会「内藤湖南、応仁の乱を論じる」「柳田國男と日本国憲法――主権者教育としての柳田民俗学」
2017年09月26日講演Ⅰ 「柳田國男と日本国憲法――主権者教育としての柳田民俗学」 大塚 英志 国際日本文化研究センター 教授
柳田國男は昭和35年、86歳の時、「最終講演」とされる席で、呻くがごとく「憲法の芽を生さなければいけない」と語った。何故、柳田は最後に「日本国憲法」を語ろうとしたのか。柳田が大正デモクラシー以降、くりかえし唱えたのは「民主主義」を可能にする「選挙民」育成のための「民俗学」であった。「妖怪の民俗学」ではなく、主権者教育のツールとして設計された柳田の学問の本質について今こそ考え、受け止めてみようではないか。
講演Ⅱ 「内藤湖南、応仁の乱を論じる」 呉座 勇一 国際日本文化研究センター 助教
戦前、東洋史家の内藤湖南は、応仁の乱を日本史上最大の事件と位置づけました。応仁の乱以後の約100年間は「日本全体の身代の入れ替わり」であると主張したのです。 しかし、応仁の乱で既存の秩序が完全に崩壊したというのは本当でしょうか。内藤はいくつかの根拠を掲げていますが、細かく検討してみると必ずしも説得力のあるものではありません。内藤はなぜ上記のような過激な説を唱えたのでしょうか?この講演では、応仁の乱そのものを細かくみていくのではなく、乱の様相を通して内藤の議論の是非を再検討するとともに、内藤説の意図や背景を探ります。

-
【民博】みんぱくウィークエンドサロン「アジアの婚礼――祝福のかたち」
2017年09月24日結婚は、人生のもっとも重要な通過儀礼の一つです。民博の展示場からは、男女の結びつきをめぐるアジア各地の多彩な儀式とさまざまな祝福をうかがうことできます。婚礼用品を通して、結婚当事者、その周囲の人間関係および自然の摂理への配慮と気持ちを考えます。

-
【民博】みんぱくワールドシネマ「おみおくりの作法」
2017年09月18日国立民族学博物館では2009年度から、研究者による解説付きの上映会「みんぱくワールドシネマ」を実施しています。9年目の今期からは<人類の未来>をキーワードに、映画上映を展開していきます。今回はイギリス・イタリア合作「おみおくりの作法」を上映します。孤独死を遂げた人を、できる限りの誠意を尽くして“おみおくり”する仕事に臨んできた民生係のジョンの姿を通して、人間関係が希薄になりつつある現代社会の中で、さまざまな人生を歩んできた人びとの尊厳ある生と死について、日本のお彼岸の季節に考えたいと思います。

-
【民博】みんぱくゼミナール 「多文化主義の国カナダにおける先住民文化」
2017年09月16日さまざまな民族が共生するカナダは、2017年に建国150周年を迎えます。先住民と国家の歴史は、対立と妥協の繰り返しでした。同国の多様な先住民文化の歴史と現状を国家との関係に着目しながら紹介します。