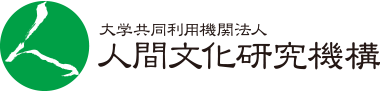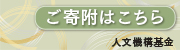展示情報一覧
【国文研】通常展示「書物で見る 日本古典文学史」
- -
本展示では、上代から明治初期までの文学を、書物(古典籍)によってたどります。最近の研究動向にも配慮はしましたが、むしろ教科書でなじみの深い作品を中心に据えて、文学史の流れを示しました。写本の表情や版本の風合いに触れながら、豊かな日本古典文学史の諸相をお楽しみください。
期間:2022年10月19日(水)~2023年1月25日(水)
場所:国文学研究資料館1階 展示室

【民博】特別展示「Homō loquēns 「しゃべるヒト」~ことばの不思議を科学する~」
【歴博】第3展示室(近世)特集展示「もの」からみる近世『水滸伝ブームの広がり』
特別展示「創立50周年記念展示 こくぶんけん〈推し〉の一冊」
- -
当館の研究者が紹介したい一冊を選び、その魅力を語ります。本物を見る楽しみにあふれた展示です。
次のようなコンセプトで展示を構成しています。
第1章の「〈推し〉の一冊」では当館に所属している日本文学、歴史学およびアーカイブズ学研究者が「推し」とする館蔵の作品を紹介するコーナーです。情報系研究者は日本文学と連携した研究を紹介しています。当館所属の研究者を知っていただくとともに、それぞれの研究者の個性について作品を通じて感じてください。
第2章の「国文研をひらく」では「自然を味わう」「あの人が書いた文字」「挿絵を楽しむ」「書物で国際交流」「古典と旅をする」「古典で遊ぶ」「今年記念を迎える本」というテーマを設け、展示ではあまり利用していない作品をご覧頂きたいと思います。
第3章の「国文研のこれまでとこれから」は当館の歴史にまつわる資料を写真とともに振り返ります。今回は当館が創立した時の品川区戸越の建物の定礎に収められていた資料を主に展示します。